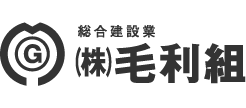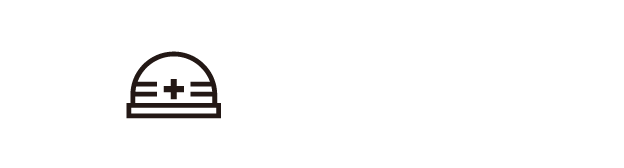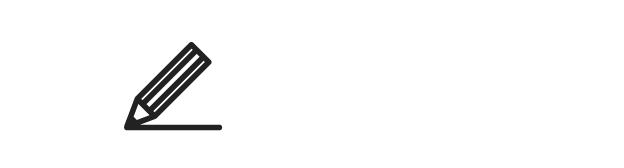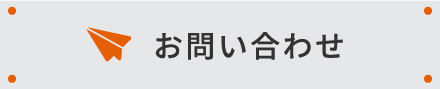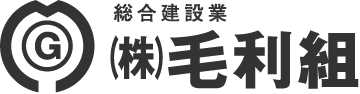ブログ
毛利組のスタッフ日記

ブログ
Staff Blog
2025.09.03 日々の出来事
防災の日って知ってた?建設業が支える“見えない備え”の話
こんにちは、毛利組の中の人です。
いつもブログをご覧いただきありがとうございます!
さて、9月1日は「防災の日」でしたね。そして、その前後1週間は「防災週間」と呼ばれています。
みなさんは「防災の日」に何か備えや備蓄品の見直しなど何かしましたか?
中の人はうっかりすっかり忘れていて、今週末に備蓄品の見直しを行おうかと・・
今回はこの機会に、「日頃からの備え」について、ちょっとだけ考えてみませんか?
なぜ9月1日が「防災の日」なの?
「防災の日」は、1923年に発生した関東大震災の教訓をもとに、1960年に制定されました。
また、9月1日はちょうど「二百十日」と呼ばれる、台風が多くなる時期にもあたります。
つまり、防災の日は「地震や風水害に備えよう」という思いが込められた日なんです。
建設業が担う“見えない防災”の仕事たち
防災と聞くと、防災グッズや避難訓練が思い浮かびやすいですが、実はもっと広い場所で“備え”は行われています。
普段見かけるあの工事も、実はあなたの暮らしを守る「防災」に直結しているかもしれません。
その一つが、私たち建設業が日々行っている仕事です。
日々の工事の中にも、じつは「防災」に直結する大切な仕事がたくさんあります。
地震に備える「橋梁の耐震化工事」
地震によるインフラ被害は、命だけでなく復旧にも大きな影響を与えます。
中でも「橋」の安全性は非常に重要。災害時に通れない橋があると、救援活動や物資輸送が大きく遅れてしまいます。
そのため、各地では古い橋の支柱を補強したり、耐震性能を高める工事が進められています。
こうした「橋梁の耐震化」は、まさに“災害に強い地域”をつくる取り組みのひとつです。
台風や豪雨に備える「河川改修工事」
近年、線状降水帯やゲリラ豪雨による水害が増えています。
川の氾濫を防ぐには、水の流れをスムーズにし、堤防を整備することが重要です。
建設業では、川底の土砂を掘り、川の流れをスムーズにする「浚渫(しゅんせつ)」や、
堤防を強くしたり、広げたりする「河川改修工事」が行われています。
これにより、雨が降っても安心できる地域づくりが進んでいるんですね。
土砂災害を防ぐ「法面工事・砂防堰堤」
山の多い日本では、地震や大雨で起きる土砂災害にも備えが必要です。
山や崖が崩れないように補強する「法面(のりめん)工事」や、
土砂が流れてくるのを防ぐ壁のような「砂防堰堤(さぼうえんてい)」なども、防災の重要な工事のひとつです。
こうした地道な工事が、私たちの暮らしを陰ながら支えてくれています。
家でも職場でもできる「小さな備え」
もちろん、私たち一人ひとりにもできる防災があります。
- 避難場所の確認
- 防災グッズの準備
- 家族との連絡手段の共有
これらは、今日からでもできる小さな備えです。
「ちょっと確認してみようかな」
その一歩が、いつか自分や大切な人を守る力になるかもしれません。
まとめ:備えは、つながる力
防災は「誰かのために備える」ことでもあります。
建設業が担うインフラ整備も、個人が用意する非常持ち出し袋も、すべては「みんなの暮らし」を守るための大切な準備。
毛利組としても、地域の皆さまとともに、防災への意識を高めながら、これからも社会に貢献してまいります!
それでは、また来週!
今週もご安全に!!